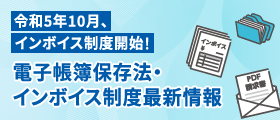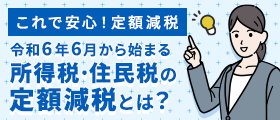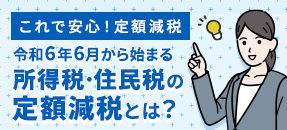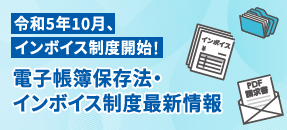当法人からのお知らせ | 2024.04.26 ホームページをリニューアルいたしました。 |


安定
創業45年の
信頼と実績!

人間力育成
社員への各種能力開発
プログラムが充実!

信頼
顧問先700社超!

支援
社員の資格取得支援に
積極的!

ワンストップ
江後経営グループの
総合力!





2024.04.23 経営ニュース
2024.04.16 経営ニュース
36協定の届け出と 時間外労働上限規制 ●3月から4月は36協定の提出最盛期です 36協定は「時間外、休日労働に関する労使協定」のことです。年度終わりの3月から新年度の4月頃に36協定を労働基準監督署に […]